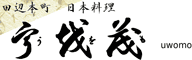豆知識(やきもの種類)

料理に使われる器には、やきものやガラス等がありますが、その中でやきものの種類についてです。やきものは大きく分けて4種類に分類されます。
その中で通常料理の器として使うやきものは、陶器と磁器の占める割合が大きいです。(ガラスや漆器もありますが)
陶器は温かみのあり、磁器は洗練された優雅さがあり、それぞれに素晴らしい個性があります。
陶器とは
陶器とは、粘土を成形が済んだところで
削ったり、取っ手をつけるなどの絵を付ける。焼き方が柔らかく、質が荒め。淡い色が多い。土の色や釉薬の
かけ具合いで模様を作る。
基本的にたたくと鈍い音がする。
朝鮮から伝来した。
磁器とは
磁器とは、陶石を粉砕したもので、素焼きをして下絵を描き、施釉して本焼き。その後、上絵を描いて焼きつける。焼きが硬く、質が細かく
気孔が少ない。白磁に染付け、赤・青や金の細かな絵付けなど派手な色が多い。
たたけばな高い音がする。
中国から伝来した。日本の中では有田が最初。
陶器
原料 有色粘土
色 有色
吸水性有り
たたけば鈍い音がする
唐津焼・薩摩焼・常滑焼・万古焼・伊賀焼・信楽焼・越前焼・丹波立杭焼・赤膚焼・萩焼など
石器
原料 有色粘土
色 有色
たたけば硬い音がする
備前焼など
土器
原料 有色粘土
色 有色
吸水性有り
たたけば鈍い音がする
縄文土器や弥生式土器
磁器
原料 白色粘土、長石
珪石、陶石
色 白色
たたけば硬い音がする
会津焼・久谷焼・有田焼・出石焼・波佐見焼・瀬戸焼・砥部焼・鍋島焼・中国景徳鎮・西欧のマイセンやロイヤルコペンハーゲンなど
日本のやきものは縄文式土器や弥生式土器に始まり、日常的に使われるようになったのは平安時代の山茶碗からで、この後に日本六古窯の陶業地が栄えました。(瀬戸・常滑・信楽・越前・丹波・備前)その後、茶道とともにうつわとして志野・織部などのやきものが焼かれました。
その後、豊臣秀吉時代の朝鮮戦役で特に九州の諸公が優れた陶工を連れて帰り、有田で磁器が焼かれたり、柿右衛門や伊万里・鍋島などができた。京都では古清水から京焼ができ、楽焼や九谷焼きなどが各地に発展しました。
|